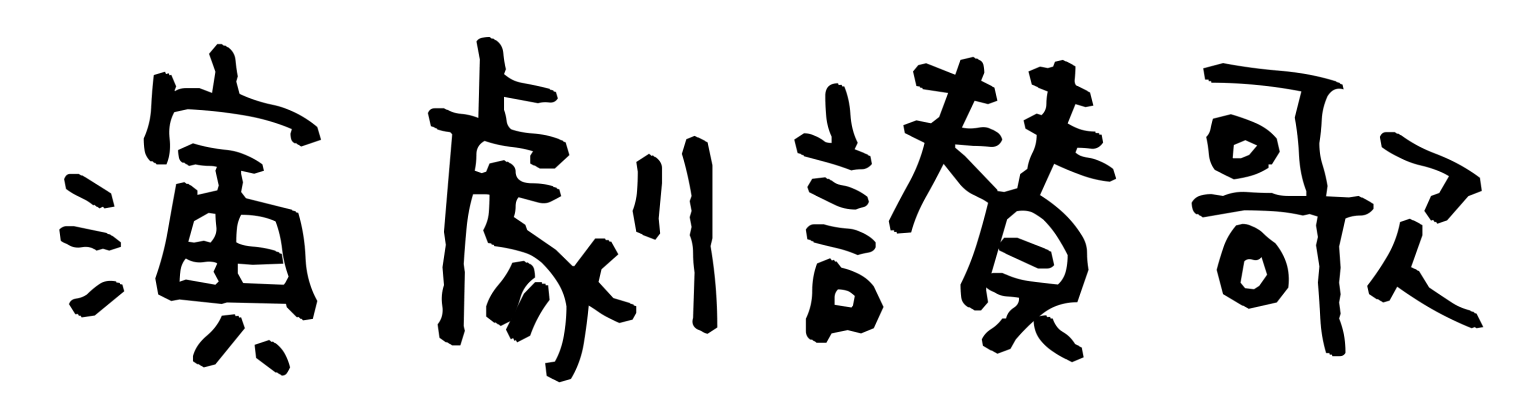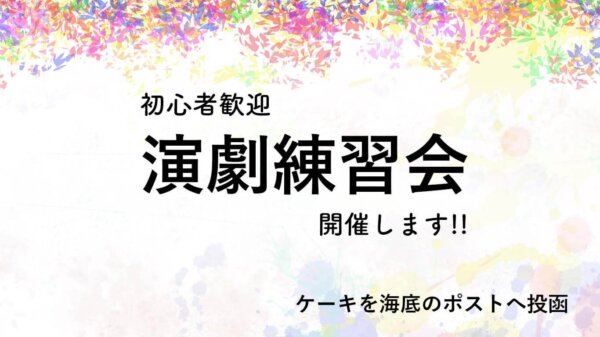はじめに俳優が知っておきたい!演劇の基本用語25選
このページでは、俳優が舞台での演技に役立てられる演劇の基本用語を体系的に紹介しています。役の理解、声や身体の使い方、テンポ・間の感覚、舞台空間や照明の捉え方、共演者や観客との関係の築き方、稽古での心構えまで、現場で使える知識と視点を(できるだけ)網羅!
初心者にもわかりやすく、経験者の再確認にもなる内容です。
🧩 Ⅰ. お話のなかの人とその感情
役とセリフ
| 用語 | 説明 |
|---|
| 役 | 物語の中で俳優が演じる人物のこと。性格や価値観、他者との関係性などが設定されており、ただ台詞を読むのではなく、役の視点や感情を理解したうえで、その人として舞台で“生きる”ことが求められる。リアリティのある演技には、深い想像力と共感力が必要。 |
| セリフ | 台本に書かれた発話内容。伝えるべき言葉そのものだけでなく、誰に対して、どんな状況下で、どんな気持ちをもって話すのかを意識する必要がある。声のトーンや間(ま)、強弱を使い分けることで、セリフが生きたものになり、観客に届く。 |
| サブテキスト | 表面上の台詞の裏にある、話者の本音や隠された感情、思惑などのこと。たとえば「ありがとう」と言いながら怒っているなど、言葉と気持ちにズレがあるときに、それをどう演技に込めるかが鍵。演技に深みを出すためには不可欠な視点。行間などという場合もある。 |
| ト書き | 台本の中で、セリフ以外に登場人物の動きや場面の状況、感情などが書かれている部分。演出や演技のヒントが含まれており、表現を考えるうえで重要な情報源となる。セリフだけでなくト書きまで丁寧に読み込むことが、自然な演技につながる。 |
舞台演劇用語:役とセリフ🗣️ Ⅱ. 声やからだを使う表現の技術
声と身体で伝える感情
| 用語 | 説明 |
|---|
| 発声 | 舞台上で言葉をはっきりと、適切な大きさや響きで届けるための声の使い方。感情や状況に応じて抑揚や速度、音量を調整することで、言葉の説得力が高まる。呼吸や姿勢との連動も意識しながら、聞き取りやすく感情のこもった発声を行う。 |
| 感情表現 | 登場人物の感情(喜怒哀楽など)を、声、表情、動作などを使って具体的に伝える技術。感情の種類に応じて身体の動きや声の質が変化することを理解し、それを意識的に表現する力が求められる。観客に心が伝わることを目指して演じる。 |
| 身体表現 | 身体全体を使って状況や気持ちを伝える方法。姿勢、手足の動き、視線、呼吸などを意識して、言葉に頼らなくても観客に情報を届ける。台詞がない場面でも、動きだけで十分に感情や関係性が表現できることがある。 |
| 視線 | どこを、どんなタイミングで見るかによって、人物の感情や集中、関心の方向が伝わる。視線を合わせる、逸らす、遠くを見るなどの使い方によって緊張感や親密さを演出できる。観客との視線の関係も意識する必要がある。 |
舞台演劇用語:声と身体で伝える感情⏱️ Ⅲ. 動き・タイミング・リズム
間とテンポで生まれる空気感
| 用語 | 説明 |
|---|
| 間(ま) | セリフや動きのあいだに意図的に作る“余白”の時間。沈黙や動作の止まりがあることで、感情の揺れや思考を表現することができる。間があることで、言葉の重みや空気感が生まれ、観客に深く伝わる演技になる。呼吸や相手の反応とも関係が深い。 |
| テンポ | セリフや動作の速さやリズム感のこと。テンポが早ければ勢いを、遅ければ重みや慎重さを表せる。場面ごとにテンポの使い分けがあり、演出や共演者との調和も重要。テンポの違いによって場の印象や感情の流れが大きく変化する。 |
| 動線 | 舞台上で演者が移動する経路。美術や照明との兼ね合いを踏まえた動きの設計によって、演技が滑らかかつ意味のあるものになる。観客が見やすく、演者同士がぶつからないように考えられている。自然な移動が演技の一部となる。 |
| 即興 | 台本なしでその場の状況に応じて自由にセリフや動きを作り出す演技の方法。反射的な反応や、相手との呼応によってリアルな場面が生まれる。柔軟性と集中力が問われ、思考力や表現力を鍛える練習としても使われる。 |
舞台演劇用語:間とテンポで生まれる空気感🏗️ Ⅳ. 空間・舞台環境に関する用語
舞台袖から照明までの舞台環境
| 用語 | 説明 |
|---|
| 舞台袖 | 舞台の横にあり、客席からは見えない場所。演者が出番を待ったり、準備をする空間。緊張と集中を高める場でもあり、「舞台へ入る」ための心のスイッチを切り替える場所でもある。照明や音響のタイミングと連動し、演技の流れに大きな役割を果たす。 |
| 照明 | 舞台を照らすライト。時間帯や感情、場面の変化を視覚的に伝える手段で、作品全体の雰囲気づくりに欠かせない。光の色、強さ、当て方によって、人物や空間の印象を変えることができる。演者は自分がどこに照明されているかも意識する必要がある。 |
| 立ち位置 | 舞台上で演者が立つ場所。前方に立てば目立ち、後方や端に立てば距離感や静かさを表せる。他の登場人物や舞台美術との関係性、観客の視線などを考えて決められることが多い。演出の意図に基づき、意味をもった立ち位置をとることが求められる。 |
| 転換 | 物語の場面が切り替わること。舞台美術や照明、音響、演者の動きによって空間や時間を変える。観客に「違う場所・時間である」と伝えるための工夫が必要。演者も場面の切り替えに合わせて気持ちを調整し、空間の変化に対応する必要がある。 |
舞台演劇用語:舞台袖から照明までの舞台環境🤝 Ⅴ. 役者同士の関係性・やりとりに関する用語
アイコンタクトとリアクションの力
| 用語 | 説明 |
|---|
| アイコンタクト | 相手と目を合わせること。視線を交わすことで、関係性や感情が伝わり、演技にリアリティが生まれる。見つめる、そらす、動かすなど視線の使い方によって、緊張感や親密さを表現することができる。舞台では観客の視線誘導にも関わる重要な技術。 |
| リアクション | 相手のセリフや動作に対して自然に反応すること。驚いたり、笑ったり、沈黙することもリアクションに含まれる。受け取る姿勢を意識することで、セリフのやり取りが本物の会話のようになり、観客に伝わる演技になる。相手をよく見る力が必要。 |
| 観客との距離感 | 舞台に立つ演者が、どれくらい観客に心や表現を近づけるかという感覚。語りかけるような演技では距離が近く、内面的な演技では距離を保つこともある。観客の視点や感情の入り方を考えながら、表現の仕方を変えていくことが求められる。 |
| 集中 | 舞台に立っている間、自分の役や状況に意識を強く向けること。他のことを考えず、その瞬間に“いる”ことができると、演技が深く伝わる。周囲の音や視線に惑わされず、物語に入り込む力が演技の質を左右する。練習によって鍛えられる。 |
舞台演劇用語:アイコンタクトとリアクションの力🎬 Ⅵ. 稽古・創作・舞台上での意識
稽古と役との距離のバランス
| 用語 | 説明 |
|---|
| 稽古 | 本番の舞台に向けて、演技や動き、舞台の流れなどを何度も繰り返して練習すること。読み合わせ、立ち稽古、通し稽古などの段階があり、演出家と話し合ったり、共演者とタイミングを合わせたりする。稽古は演技だけでなく、作品全体を育てる大切な時間。 |
| 通し稽古 | 舞台の最初から最後までを、実際の順番や流れで通して演じる稽古。全体のテンポ、場面のつながり、気持ちの移り変わりなどが確認できる。本番に近い形で動くことで、個々の演技だけでなくチームとしての完成度を高めることができる。 |
| 演出への応答力 | 演出家の指示や修正に対して、ただ従うだけではなく、自分の役や考えに合わせて工夫しながら取り入れていく力。演出の意図を理解しながら、役の中で自然に表現できるようにすることで、作品の質を高める共同作業につながる。 |
| ルールと自由 | 演技には動き方やセリフの順番など「決まり」がある一方で、自分らしい表現を加える「自由」もある。決まりだけを守っていては硬くなりすぎるし、自由すぎるとまとまりがなくなる。両方のバランスを取ることで、良い舞台ができる。 |
| 役との距離の保ち方 | 演技では役に深く入りこむことが必要だが、完全になりきってしまうと感情的になりすぎてしまうこともある。俳優としての自分の目線を少し残しておくことで、冷静に演技を調整できる。没入と客観のバランスが長く続けるうえで大切。 |
舞台演劇用語:稽古と役との距離のバランスこのページでは、俳優として舞台での表現を支える演劇の基本用語?たちを、できるだけ体系的にわかりやすく解説しました。役への向き合い方、身体と言葉の使い方、テンポや空気感のつくり方、空間と観客との関係性、そして稽古・創作への姿勢がさわりだけでも掴んでいただけたのではないでしょうか?
演劇が初めての人にも、長く舞台に立っている人にも、自分の演技を言葉で理解し、伝える力を高めるきっかけとなれば幸いです。